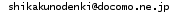第一種電気主任技術者 / 試験基本情報
☆電気主任技術者の資格とは
電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、
電気主任技術者を選任しなくてはならないことが、電気事業法により義務付けられております。
電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、
電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。
☆一種、二種、三種それぞれの適用範囲について
| 【事業用電気工作物】 | ||
| すべての事業用電気工作物 | 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く) |
| (例)上記電圧の発電所、変電所、送配電線路や電気事業者から上記電圧で受電する工場、ビルなどの需要設備 | (例)上記電圧の5千キロワット未満の発電所や電気事業者から上記の電圧で受電する工場、ビルなどの需要設備 | |
| ★第三種電気主任技術者★ | ||
| ★第二種電気主任技術者★ | ||
| ★第一種電気主任技術者★ | ||
試験について
第一種電気主任技術者試験は、一次と二次の2回行われます。
☆一次試験の内容
- 【理論】(A/4題、B/2題※)
- 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測
- 【電力】(A/4題、B/2題)
- 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む)の設計及び運用並びに電気材料
- 【機械】(A/4題、B/2題※)
- 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理
- 【法規】(A/4題、B/2題)
- 電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理
<備考>
・解答数欄の※印については、選択問題を含んだ解答数です。
・法規科目には「電気設備の技術基準の解釈について」(経済産業省の審査基準)に関するものを含みます。
☆二次試験の内容
- 【電力管理】(6題中4題を選択)
- 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む)の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの
- 【機械・制御】(4題中2題を選択)
- 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの
☆出題形式
- 一次試験の出題形式
- 各科目の解答方式は、マークシートに記入する多肢選択方式です。
- 二次試験の出題形式
- 各科目の解答方式は、記述方式です。
試験における各種制度
☆科目別合格制度
一次試験は科目ごとに合否が決定され、4科目すべてに合格すれば一次試験の合格となります。
また、4科目中一部の科目だけ合格した場合は、「科目合格」となって、
翌年度及び翌々年度の試験では申請により当該科目の試験が免除されます。
つまり、3年間で 4科目に合格すれば、二次試験の受験資格を得ることができます。
二次試験には科目別合格制度はありませんが、一次試験合格年度において二次試験不合格となった場合は翌年度の一次試験は免除となり再度二次試験を受けることができます。
しかし、翌年度の二次試験において再び不合格となった場合は、再度一次試験(4科目すべて)から受験することとなります。
☆認定による資格取得のための単位が不足している方(単位不足者)のための試験制度
電気主任技術者免状を取得するには、主任技術者試験に合格する以外に、認定校を所定の単位を修得して卒業し、
所定の実務経験を得て申請する方法(学歴と実務経験による免状交付申請)があります。
この申請方法において、認定校卒業者
(電気事業法第44条第2項第1号で定める学歴及び実務経験による試験取得希望者をいう)
であっても所定の単位を取得できない方は、その不足単位の授業内容が含まれる試験科目に合格し、
実務経験等の資格要件を満たせば、免状交付の申請をすることができます。
ただし、この単位取得とみなせる試験科目は、「理論」を除く「電力」「機械」「法規」の 3教科目のうち
「法規」を含む 2科目までで、「電力と法規」又は「機械と法規」の 2科目か、
「電力」「機械」「法規」のいずれか 1科目に限られます。
受験申込み方法
☆インターネット申込みの場合
- ・試験センターのホームページ
- http://www.shiken.or.jp/ から画面の案内手順・注意事項にそって進んでください。受付期間は平成26年5月19日(月)午前10時~6月13日(金)午後5時までです。
- ・新規申込み
- 画面の案内手順・注意事項にそって入力してください。
- ・科目合格留保者の申込み
- 合格証明書の番号が記載されたハガキなどを確認の上、画面の案内手順・注意事項にそって入力してください。
- ・支払方法
- 受験手数料(12,400円)は、銀行口座振込決済・クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済・ Pay-easy(ペイジー)決済 の4種類から選択してお支払いください。 ただし、団体申込みのときは銀行口座振込決済のみとなります。振込手数料や事務手数料は申込者の負担となります。
- ・団体申込とは
- 2名以上で申し込みをする場合は、法人・学校など組織に関わらず「団体申込み」とすることができます。 受験手数料は、団体代表者が受験者全員分を一括で支払います。 なお、団体代表者は、受験申込者でなくても問題ありません。
- ・受験票ならびに試験結果通知書について
- 受験票や結果通知は、個人申込み・団体申込みに関わらず、各々の受験者宛に送付されます。
☆郵便申込みの場合
受験案内に綴じ込まれている新規受験者用の申込書①または科目合格留保者用の申込書①(以下受験申込書①という)を使用し、
受験申込書の記入要領を参考にして必要事項を記入の上、
平成26年5月19日(月)~6月6日(金)まで(当日消印有効)<<すでに終了しています>>に、
受験手数料(12,800円)及び振込手数料とともにゆうちょ銀行(郵便局)窓口に提出してください。
記入は、黒ボールペン等を使用し、かい書で正確に記入してください。
記入事項を訂正する場合は、当該箇所を二重線で消し、余白部分に訂正してください。
[注意事項]
(a)郵便局等に備え付けの振込用紙は受験申込に使用できません。
必ず受験案内に綴じ込まれている申込用紙を使用して、郵便局の窓口で振込みをしてください。
(b)受験申込書①の申込者の住所、氏名欄は、必ず受験者と同一人としてください。
(c)受験手数料を郵便局ATMから直接、所定の口座番号に振り込まれるなど他の方法を利用された場合の申込は受付されません。申込受付後の受験手数料は、自己都合による取消しの申出や試験日に欠席された場合でも返却いたしません。次回以降の試験への充当もしません。
(d)受験申込書①の記入内容に不備がある場合、文書又は電話等にて申込者に問い合わせをする場合があります。
このため電話番号は申込者本人と常時連絡のとれる番号を記入してください。
持ち込み電卓についての注意事項
☆使用可能な電卓
電池(太陽電池を含む)内蔵型電卓で音の発しないもの
(四則演算、開平計算、百分率計算、税計算、符号変換、数値メモリ、電源入り切り、リセット及び消去の機能以外の機能を持つものを除く)に限ります。
なお、「四則演算、開平計算、百分率計算、税計算、符号変換、数値メモリ、電源入り切り、リセット及び消去の機能」とは、
電卓のキーの働きが「3.使用可能な電卓」に示されているキーの機能表示の範囲に対応します。
詳細は、受験申込方法(案内) をご覧ください。
試験勉強に必要な期間のめやす
☆時間の無い方(お仕事されている方)
- 一発合格を目指す方
- 【初学者】おすすめしません
【学位・資格保持者】1年~2年 - 科目合格を目指す方(1科目当たり)
- 【初学者】おすすめしません
【学位・資格保持者】3ヶ月~8ヶ月
☆時間の余裕がある方(お仕事をされていない方・学生等)
- 一発合格を目指す方
- 【初学者】1年~2年
【学位・資格保持者】6ヶ月~12ヶ月 - 科目合格を目指す方(1科目当たり)
- 【初学者】6ヶ月~12ヶ月
【学位・資格保持者】2ヶ月~6ヶ月
※「学位取得者」とは、理工系大学卒業相当の方を指します。「資格保持者」とは、
第一種電気工事士・第三種電気主任技術者・エネルギー管理士・1種冷凍機械責任者・特級ボイラー技士のうち2つ以上お持ちの方を指します。